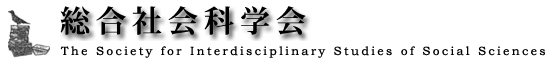第11回 総会・研究大会
【プログラム】
日程:2009年6月14日(日)
会場:日本大学 文理学部 図書館(3階)オーバルホール
〒156-8550 東京都世田谷区 桜上水 3-25-40
11:00~
受 付
11:30~11:50
総 会
12:00~14:25
研究発表 (発表30分、質疑応答15分)
14:35~16:20
シンポジウム
16:30~18:00
特別講演 (講演60分、質疑応答30分)
18:00~
懇親会 (大学構内)
研究発表および特別講演要旨
コメニウス著『汎教育』における教師論に関する一考察
――「楽しさ」に焦点を当てて――
笹川 啓一
教育史において、コメニウス(Jan Amos Comenius, 1592-1670)は体系的教育書である『大教授学(Didactica Magna)』を執筆した近代教育学の父として知られている。彼に関する研究の多くはこの書に依拠しているが、晩年に執筆された『汎教育(Pampaedia)』を扱った研究は今まで僅かである。
『大教授学』においては「僅かな労力で 愉快に 着実に教わることのできる(中略)方法」として教授論の中での「楽しさ」が述べられ、『汎教育』においても「個々の『人間』の精神がさまざまの快楽を育む庭園となるように」と執筆目的を明示し、両書で「楽しさ」というテーマを追求した。更に、『汎教育』の中に「汎教師」という章を設け、『大教授学』では詳しく述べられなかった教師論を考察している。
そこで、本発表では現代の教育での「楽しさ」を追求する手がかりになることを意図して、両書で追及し続けた「楽しさ」と関連させて彼の教師論を取り上げて論じたい。
G・H・ミードの杜会的自我論における倫理的性格
塩田 智子
諸個人は、それぞれに異なった生活をしているが、しかしそれと同時に、自らと異なる「他者」達と共に生きている。他者達と関係をもつにあたっては、様々なルールが必要であり、それは例えば、法律や常識や慣習といったようなものである。異なる他者達といかに生きていくかという問いは、通信や交通の技術が発達し、国際杜会へと開けてきた今日において、より真剣に向き合わなければならない問いであろう。とはいえそれは、国際交流といった点においてのみ問われるものではなく、多様なコミュニティに属する諸個人達の日常生活においても向けられる問いである。
倫理学において重要なことのひとつは、普遍妥当性(あるいは普遍化可能性)の追求である。それは端的に言うと、いつでもどこでも誰にでも通用する倫理を探求することを意味する。例えば功利主義について言うならば、倫理において本来求められるはずである普遍妥当性の積極的な追及、それを欠いてしまいかねないという弱点が挙げられる。
さて、本発表で取り扱うG・H・ミードは、倫理の普遍妥当性の追及に対して、彼なりのアプローチをみせている。彼は、社会的自我論のコミュニケーションに関する考察において、自己と他者の相互行為、また主観的自我(主我)と客観的自我(客我)の相互作用に着目することで、普遍妥当性の探求に挑んだ。それは、自己と他者や主我と客我に生じる間題状況(例外的事例など)を解消し、間題解決に至るという弁証法的な方法である。ミードは、カント倫理を考察するなかで、定言命法において一体何が道徳的行為なのかということをカントが明言していない点を指摘し、「行為に二者択一の仕方があると想定するなら、何が正しいのかという決定的な手段としてカントの動機を利用することはできない」(G・H・Mead, Mind,Self,Society)と述べる。すなわちミードは、先にも述べた問題状況において、外的には他者とのコミュニケーション、内的には自身とのコミュニケーションが必要であると説き、自己と他者及び主我と客我における了解をもって、倫理の普遍化可能性を獲得するとしている。
こういったミードの思索は、一見、功利主義やカントの問題を打破する糸口としてひとつの有効な見解を提示していると思われるが、検討を要する間題点もまた内包している。それは、例えば、全ての人カと対話するということは実際の間題として不可能であるということである。今回は、そういった間題点にも配慮しつつ、発表したい。
演劇における上演と受容の諸問題
――マリヴォー『いさかい』を例として――
奥 香織
小説を読むことが「私的な経験」であるとすれば、演劇を観ることは「集団的な経験」であるといえる。それは、多くの人と同じ時間と場所を共有するという意味においてだけでなく、ある演出家が提示する「ひとつの解釈」を共有するという点においてである。
マリヴォーの『いさかい(La Dispute)』は、1744年、フランス人劇団(コメディ・フランセーズ)によって初演されたが、完全な失敗に終わり、一回の上演で忘れ去られる。その後、1938年に同劇団が再び上演を試みるが、反響はなかった。しかし、1973年、パトリス・シェローの斬新な演出がセンセーションを巻き起こし、『いさかい』は「新たな作品」として生まれ変わる。子供たちの野生的な側面と実験の非情さが強調されたシェローの演出は、『いさかい』という作品を世に広めただけでなく、この作品に新たなイメージを付加することになった。シェローの『いさかい』は、どこまで「マリヴォー」なのだろうか。
本発表では、『いさかい』の18世紀的読みとシェローの解釈の差異を分析し、演劇における上演と受容の諸問題を考察する。
【シンポジウム】
経済的合理主義は「合理的」か
――日常生活の中の「合理性」――
コーディネーター(司会)
高頭 直樹
近年、さまざまな分野で進められた「グローバリゼイション」は、経済的合理性を高めることで「合理的社会」の構築を目指したものだといえるであろう。
しかし、その結果、我々は、現在さまざまな「不合理」に直面している。「合理的動物」と呼ばれるわれわれ人間の社会の中で、本来多義性を持つ「合理性」はいかに追及されるべきか、本シンポジウムでは、この問題を改めて検討することとする。
「グローバリゼイション」と合理性
パネリスト
石川 修一
いま、国境の壁を前提とした「インターナショナリゼィション」ではなく、ボーダレスに人、物、マネーが移動する「グローバリゼイション」が大きく進展している。このために、様々な分野で「グローバリゼイション」にともなうグローバルスタンダードの整備がもとめられている。
一方で、本来、世界の様々な地域の多様性な価値あるいは多義的なものを「グローバリゼイション」は、経済合理性に基づき一つのスタンダードで整理しようとしている結果、そのせめぎあいの中で我々は現在さまざまな「不合理」に直面している。このような「グローバリゼイション」の目的設定に合理性があるのか。また、「合理性」とは本来なにかについて改めて検討する。
本当の「経済合理性」とは何か
パネリスト
八田 隆司
現在、世界は「100年に一度の不況下にある」といわれている。そのため従来の「経済的価値観」や「経済的ありかた」が、グローバル化による「雇用の不安定化」や「格差・貧困問題」ともあいまって、再検討が迫られるようになった。
「経済合理性」として一般に考えられていることの意味は、「経済的効率性」である。この「経済的効率性」の追求によって、資源を無駄なく、富を効率的に生産することができるとされている。しかしこのような「経済的効率性」が本当に人々に生活の満足度、さらに言えば「生きること」への充実感を与えているのだろうか。今回の発表において、「経済的効率性」は、本当に経済的に合理的なのかどうなのかを、問題にしたい。それを論じていくための論点を以下に、述べておく。1、「経済的効率性」でいわれる「効率」とは、有限な資源と所与の技術・選好の制約の下で、できるだけ多くの欲求を満たすように、できるだけつつましい行動を合理的に選択することだと言われている。そうであれば、「効率性」とは「欲求の充足」を達成するための手段である。
2、「経済合理性」を「経済効率性」としてとらえるならば、「人間生活の営み」である経済の「合理的根拠」は、「欲求の充足」であることになる。本当に「人間の生きる」ことは、「単なる欲求の充足」という点にあるのだろうか。この問題を功利主義の人間把握を通して、論ずる。
3、「人間は社会的動物である」といわれているように、人間の自己形成は他者関係である社会とのかかわりにおいてなされるという考えに立てば、「欲求充足」のためだけに人間は生きているのだろうか。この問題を、共同体における「相互承認」という観点から論じていく。
4、自と他との相互承認が成立するためには、自他の生活基盤である共同体に何が必要か。自他の共通の生活基盤を機能させるものとして「共感」の働きに着目したい。他者の問題を「自分の問題」として感ずる力が、相互承認の前提になるからである。
5、共同体における「共感」の働きを重視した思想家の一人にアダム・スミスがいる。スミスは、今日の経済不況の元凶と目されている。しかし「経済的自由な活動」が成立する基盤に「共感」をおいており、その共感が成り立つ「共同体」のあり方として「農業」の重要性を説いている。
6、上記の観点から、今日の日本の「公共事業」に見られる問題点を考えながら、「相互承認」による「生活の満足」を向上させる共同体のあり方を、つまりもっとも効果的に「共感」が発揮される「共同体」のあり方を、論じてみたい。
【特別講演】
新しい日本文化論の試み
――『死者の書』を完結させる――
安藤 礼二
民俗学者にして国文学者、さらには釈迢空の筆名で短歌・詩・小説、すなわち日本語表現のあらゆるジャンルで作品を残した折口信夫(1887-1953)。折口は、最晩年、第二次世界大戦末期に刊行し、生涯で唯一完成することのできた自らの代表作『死者の書』の続篇となる小説作品を書き継ぎ、結局は未完のままこの世を去った。その新たな『死者の書』は、高野山奥の院の霊窟に生きながら入定した空海と、空海が唐の都長安からこの列島にもたらした西域の秘法、「光り輝く聖なる教え」をめぐる不可思議な物語だった。折口は、この新たな『死者の書』で、一体何を描こうとしたのか。また『死者の書』に秘められた謎は本当にすべて解き明かされているのか。折口信夫の最大の作品、『死者の書』の謎を解き、その物語に真の完結をもたらしてみたい。
本学会会員、多摩美術大学准教授、安藤礼二(本名:安島眞一)氏は2006年、『神々の闘争 折口信夫論』で芸術選奨文部科学大臣新人賞を、そして本年、『光の曼荼羅』で大江健三郎賞、伊藤整賞を相次いで受賞されました。
本学会は、安藤氏の受賞に心よりの祝意を表すとともに、今大会における特別講演をお願いいたしました。
第11回総会
2009年6月14日 於 日本大学